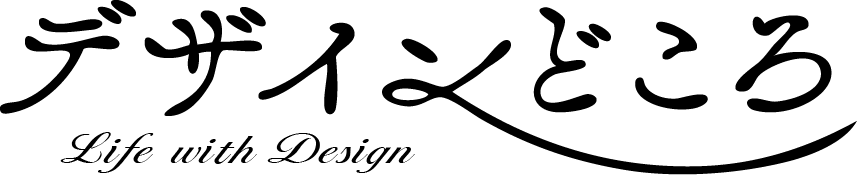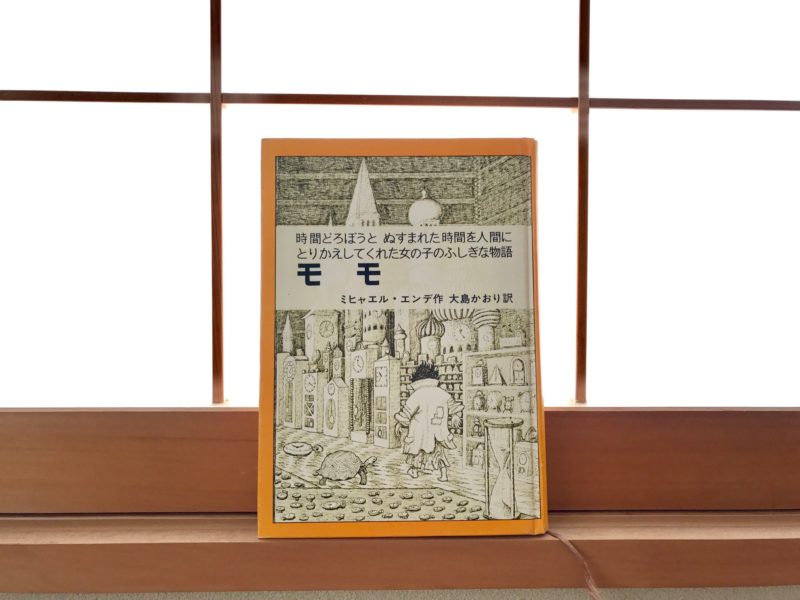31,536,000秒
これは一年間の秒数です。4月も過ぎ去り、2017年の3分の1が終わりました。
年をとるにつれ、時間が経つのは早いなぁと感じるのですが、物理的な長さが変わったわけではありません。
そんなときに目に留まったのが、実家の本棚に眠っていた児童文学の『モモ』(ミヒャエル・エンデ作)。浮浪児の少女のモモが、「灰色の男たち」(時間どろぼう)に盗まれた都会の人々の「時間」を取り戻す物語。
慌ただしい現代社会に生き、子どものときの時間感覚を失いつつある自分に、日々の暮らし方のヒントを与えてくれるかもしれないと感じ、再読しました。
1、時間を節約した先にある時間
私は「時短テクニック」や「スキマ時間で効率よく」などの言葉があまり好きではありません。そういうモノを試したことはあるのですが、どれも長続きしない、本当に良いと思ってやっているものではないので、身に付かないのです。
『モモ』では、「灰色の男たち」が人間に時間を節約することを指南します。その結果、人々は逆に時間に追われるようになり、仕事のやり方や日々の過ごし方、人格までも変えてしまうのです。
本書にはこう書かれています。
時間をケチケチすることで、ほんとうはぜんぜんべつのなにかをケチケチしているということには、だれひとり気がついていないようでした。じぶんたちの生活が日ごとにまずしくなり、日ごとに画一的になり、日ごとに冷たくなっていることを、だれひとり認めようとはしませんでした。
でも、それをはっきり感じはじめていたのは、子どもたちでした。というのは、子どもと遊んでくれる時間のあるおとなが、もうひとりもいなくなってしまったからです。
けれど、時間とはすなわち生活なのです。そして生活とは、人間の心の中にあるものなのです。
人間が時間を節約すればするほど、生活はやせほそって、なくなってしまうのです。
モモが暮らす街では、魅力的な職業の人たちが登場します。なかでもモモの友だち二人(無口なおじいさんの道路掃除夫ベッポと、おしゃべりな若者の観光ガイドのジジ)は、正反対な時間の使い方にとても惹かれるものがあります。
ベッポは、自分の仕事をとても気に入っていて、毎朝夜が明ける前に町へ行き、道路を一歩一歩ていねいに、愛情をこめて掃除します。ジジは、空想力に富んでおり、観光客相手に自分でつくった物語を話してお金を稼ぎます。いつか有名に、お金持ちになりたいという夢があります。
ゆっくりコツコツやる仕事、空想や夢から生まれる仕事
どちらも「効率を考えていない」「現実的でない」などと節約の対象になってしまいそうですが、彼らはとっても豊かで実りのある時間をつくりあげています。
それは、ただ単に「仕事(労働)」と割り切っているのではなく、自身の「暮らし」や「生き方」と結びついているからだと感じました。
2、じぶんの心で感じて生きていく
「自分の時間」とは、自分のためだけに使う時間のことではありません。誰かと一緒に過ごす時間、誰かのために使う時間も、「自分の時間」になります。
なので、「自分の時間」とは、「自分の心で感じたり、考えたり、決定したりすることができる時間」なのではないかと思います。
本書では、モモがたどり着いた「時間の国」で出会った、時間をつかさどる老人マイスター・ホラの言葉がそのことを表しています。
人間というものは、ひとりひとりがそれぞれじぶんの時間を持っている。そしてこの時間は、ほんとうにじぶんのものであるあいだだけ、生きた時間でいられるのだよ。
時計というのはね、人間ひとりひとりの胸の中にあるものを、きわめて不完全ながらもまねて象ったものなのだ。光を見るためには目があり、音を聞くためには耳があるのとおなじに、人間には時間を感じとるために心というものがある。そして、もしその心が時間を感じとらないようなときには、その時間はないもおなじだ。
私は以前、【「幸せ」をこしらえよう。】の投稿の中で、「ブラックなデザイン会社を、世の中からなくしたい」と書きました。ですが、サービス残業が必ずしもすべて悪だとは思いません。
「残業をしない、するな」ということも、時間の節約です。それを削るかどうかは、やはりそれが「自分の心がなにを感じとるか」だと思うのです。
『モモ』を読み、改めて自分の時間を生きたいと強く感じました。仕事で学んだことを日々の暮らし方に活かし、そして人生において大事にしている考えや信念を仕事でも果たしていく。それができれば、時間どろぼうなんて怖くない。
時間を大切にしたい、童心に返りたいと願っている方は、ぜひ読んでみてください。昔読んだことがある人も、大人になってもう一度読んでみることで、きっと新しい発見があるはずです。