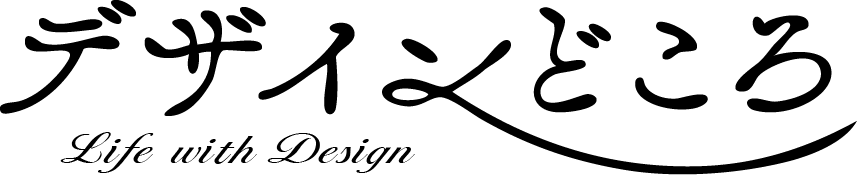先日(2023年5月16日)、「スウェーデン・ジャズ・ウィーク2023」のプログラムの一つとして、宝生能楽堂にて上演された「能とスウェーデン・ジャズの邂逅」を鑑賞してきました。能を観ることも、能の舞台で演奏されるジャズを聴くことも、私にとって未知の体験でした。
能とスウェーデン・ジャズの邂逅
「スウェーデン・ジャズ・ウィーク2023」は、スウェーデン独立500周年のナショナルデーを日本でお祝いするために、スウェーデン大使館とスウェーデン・ジャズを長年日本に紹介しているレーベルである「スパイス・オブ・ライフ」によって企画された音楽イベントです。
スウェーデン・ジャズと聞いて真っ先に思い浮かぶのが、ビル・エヴァンスの名曲『Waltz for Debby(ワルツ・フォー・デビイ)』を、母国語のスウェーデン語歌詞の『Monicas Vals(モニカのワルツ)』でヒットさせたMonica Zetterlund(モニカ・ゼタールンド)です。(→映画『ストックホルムでワルツを』で彼女のことを知った時の記事:2人の「Waltz For Debby」)
私は今回のイベントで二つのプログラムに参加いたしました。一つが、元々好きだったLars Jansson Trio(ラーシュ・ヤンソン トリオ)の六本木Satin Dollでのジャズライブ、そしてもう一つが、Isabella Lundgren & Her Trio(イザベラ・ラングレン トリオ)による「能とスウェーデン・ジャズの邂逅」でした。

演目
能の世界
能「天鼓」より一部上演
スタンダード・ジャズの世界
1. スマイル
2. カムフライ・ウィズ・ミー
3. この素晴らしき世界
4. ライフ・イズ・ジャズト・ア・ボウル・オブ・チェリー
5. 虹の彼方へ
能とスウェーデン・ジャズの邂逅
仕舞「井筒」
スウェーデン民謡
Underbart är kort「素晴らしいことは儚い」
Jag unnar dig ändå allt gott「君の幸せを願っている」
スウェーデン民謡と能の舞
Ack Värmeland, du sköna「麗しのヴァルムランド」
演目をご覧いただくと分かる通り、まず能とジャズ、それぞれの王道を演舞・演奏し、それから邂逅のシーンへと移ります。「スウェーデン民謡と能の舞」では、ジャズの醍醐味とも言える即興の演奏と、シテ方宝生流能楽師の武田孝史氏による即興の舞のコラボレーションを堪能することができました。
ジャズという音楽はアメリカで生まれて100年以上経ちますが、この音楽文化の種はあっという間に世界中に広がり、それぞれの国の個性を持った音楽となりました。
出典:当日配布のパンフレット
特にスウェーデンはジャズの誕生から直ぐにこの音楽文化を取り入れ多くのジャズ・アーティストを生み出しました。
その大きな特徴は古くからのスウェーデン民謡の影響を受けた極めて心に優しいメランコリックなメロディーにあります。
スウェーデンを代表するジャズ・シンガー、イザベラ・ラングレンと彼女のトリオによるスウェーデン民謡と能のコラボレーション。
日本の伝統芸能である能の世界を失わないように照明は能楽堂の機材をそのまま使用し、音響もなるべく自然なアコースティク感のあるコンサートといたします。
まず静と動の「対極」を見せてから、徐々に寄り添い混ざり合う演出は、とても心動かされるものがありました。能の舞から感じ取れる舞台と身体が美しく広がっていく感覚、そして、歌い手の母国語(スウェーデン語)という英語よりも自由自在に奏でやすい言葉が音楽と舞に溶け込んでいく柔軟性、それらを一言で表現するなら「余白」と言えるかもしれません。
自由な芸術、自由な音楽
「能は厳格な芸術で、ジャズは自由な音楽である」それが最初に抱いていた印象でした。確かに能を初めて観て、神聖で張り詰めた緊張感の漂う舞台芸術だと感じました。能楽師の一挙手一投足に息を呑んで見入ってしまうシーンが幾度もありました。
しかし、それと同時に能の「自由さ」も感じました。それはジャズとのコラボレーションを観て体感した「余白」から生み出されるものなのではないかと思いました。

能という芸術についてあまり詳しくなかったため、『能の読みかた』(著者:林望)という本を読んで勉強しました。そこで、自分が受け取った感覚的な「自由さ」を具体的に言語化されている箇所があり、そこに大きな学びがありました。
能は、がんじ搦めの古くさい伝統芸能だと思い込んでいる人も多かろう。けれども、それも違う。
謡曲の形で書き留められた、テキストとしての情報は、いわばまったくの「骨格」に過ぎない。それを、どう肉付けして、演技として見せるかということは、あげて役者の「解釈」にかかっている。そこには、広くて自由な、解釈の幅があり、工夫の余地がある。どういう面をかけ、どうゆう装束を附けるか、そこにも、自由裁量の幅が残されているのが、能という芸能の生命である。私が最初に能に接して驚いたのは、まずもってこの自由闊達なところであった。
役者による「自由な解釈の幅」が能にあるということが、私にとって新たな発見でした。もちろん能の舞台は神秘的で格式高い空間なのですが、それでいて演者にとっても観客にとっても、人間の豊かな想像力を発揮させることができる「余白」を持ち合わせているところに共感しました。
その点からも、解釈の幅がある能と即興による演奏が中心のジャズは、対局に位置する芸術ではなく、親和性があると言えるのではないでしょうか。自由な芸術、自由な音楽。それが、「能とスウェーデン・ジャズの邂逅」を鑑賞して見つけた一つの答えでした。
この素晴らしき世界を生きる
演目の中で『What a Wonderful World(この素晴らしき世界)』をイザベラ・ラングレン トリオが演奏されたのですが、この世界に生きる喜びを歌ったジャズの定番であるこの曲と、能の舞台空間の美しさがとてもリンクして見えたので、最後にそのお話をしたいと思います。
能楽堂という建物の、コンクリートの天井は無いものと思って下さい。
青空のもと、きらきらする水面に、不思議の橋が浮かんでいる。空中の橋である。その橋には屋根があり(もちろん屋根は無くてもよい)、松の梢が橋の欄干まで、辛うじて届いている。白洲梯子なんかは、これまた無いと思わねばなるまい。
そういう超常的空間が、目前に出現している。
そこそこに、この世のものでない「モノ」が現われる。
能を見る、というのは、そういう経験なのである。
能の舞台は「天の浮き橋」、そして、この世とは違う「超常的空間」、神々の宿る場所。
初めて能の舞台を観て「なんて素晴らしい世界なんだ」と言える世界を作り上げているように感じました。そして、そんな世界を今私は生きているのだと、心から思えた素敵な体験になりました。