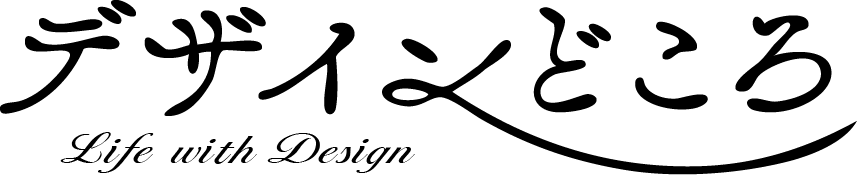私は今、雑誌『ナショナルジオグラフィック』の最新号(2023年5月号)にある「極北の野生を記録する」の記事に掲載されている、フィヨルドの写真を眺めている。ノルウェー領スヴァールバル諸島のサッセンフィヨルドだ。私にこの場所を思い出させてくれたのは、とある小説に登場する一人の女性だった。
ミッドナイト・ライブラリー
小説『ミッドナイト・ライブラリー』は、主人公のノーラ・シードが「選ばなかった人生」を冒険する物語だ。飼っていた猫を亡くし、仕事をクビになり、話を聞いてくれる家族や友人もおらず、人生のどん底にいたノーラは自死を選ぼうとする。そんな真夜中に不思議な図書館に迷い込み、高校時代に学校の図書室で一緒にチェスをした司書のエルム夫人に出会う。そこで彼女から下記の言葉をかけられる。
「生と死の狭間には図書館があるのです。この図書館の書架には涯がありません。そしてここにあるどの本もが、あるいはあなたが生きていたかもしれない人生へと誘ってくれる。もしもあの時違う決断をしていたら物事はどれほど違っていたか。それを教えてくれるのです──もし後悔をやりなおせるとしたら、やっぱり違う選択をしてみたいかしら?」
「いいですかノーラ。この図書館が存在している間は、あなたは死を免れていられます。ですからあなたはこの場所で、改めて〝自分がどう生きたいのか〟を決断しなくてはなりません」
「選ばなかった人生」というのは、「あの時ああしていたら」「ああしていなかったら」という、人間の後悔がもとになって生まれる。そして、一度でもその世界線を生きている自分自身の姿を想像したことがある人にとっては、ノーラの気持ちに共感できるところもあるだろう。
物語の中で、ノーラはさまざまな人生を旅する。水泳を続けていてオリンピックの選手になっている人生、音楽とバンドを続けていて売れっ子になっている人生、結婚して夫と子供がいる人生など。ノーラが最終的にどんな決断をしたのかは小説を読んで欲しいのだが、その中でも私は「氷河の研究者になっている人生」に共感を覚えた。なぜならそこには、私が行ってみたいと思っていた場所での出来事が描かれていたからだ。

スヴァールバル諸島との邂逅
「冬に北欧へ行ってオーロラの写真を撮ってみたい」それが私のかつての夢だった。「かつての」としたのは、『ミッドナイト・ライブラリー』を読むまでその夢を忘れかけていたからだ。2019年末から世界を席巻した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、人々の生活や人生の選択肢を一変させるほどの強大な影響力を与えた。
私自身もデンマーク行きの予定が白紙になり、それからというもの「現地に行って何かをすること」にあまり意義を感じなくなってしまっていた。(→当時のブログ記事はこちら)しかし、それまでの自分は、自分の目で見たものや肌で感じたものをこのブログに書いたり、リトルプレスのテーマにしたいと考えていた。
十一歳の頃、スヴァールバル諸島の記事を広げてじっと写真を眺めていたことは忘れない。北極海にある、ノルウェー領の群島だ。その時の雑誌は父が買ったものだった。景色は広大で孤絶して、かつ力強くも見えて、ここに身を置いたらどんな気持ちになるだろうと思いを馳せた。たとえば極圏を探査する科学者のチームに加わって、ひと夏を地勢の調査に費やすのだ。
『ミッドナイト・ライブラリー』の主人公ノーラがスヴァールバル諸島と邂逅した時のシーンが、かつての自分自身と重なった。私も北欧について調べた時にこの群島の存在を知り、いつか訪れてみたいと思っていたからだ。氷と雪に覆われた世界、見たこともない野生動物、夏は白夜で冬は極夜という環境の変化、美しいオーロラの風景、それらすべてを人生で一度は体験してみたいと思った。
ノーラは「選ばなかった人生」を旅する中で、氷河の研究者になるという夢を叶えた。極北の地での生活で彼女が感じたことや出会いの数々が、私はこの小説の中で一番印象に残っている。
今ならばノーラにも、自分を受けいれるとはどういうことか、多少は想像できる気がした。自分がやらかしてきた数々の過ち。体に刻まれた傷のすべて。手の届くことのなかったあらゆる夢と、そのたびに感じた痛み。やり過ごしてしまった欲望に願い。
そうした一切を、そのまま受けいれることを想像した。それはたぶん、自然がそこにあることを理解するのに似ている。氷山やツノメドリや、あるいは鯨による水面の盛り上がりといったものと同じように、ただそこにあると認めるのだ。
ノーラは自分自身を、自然の生み出した素晴らしくもいびつな異種の一つと見做してみようとした。自分は所詮、ただの意識を持った動物だ。それでも必死に生きようとしている。
自然の一部であることはすなわち、生きようとする意志の一部であるということだ。
あまりに長く一箇所にいすぎると、世界がどれほど果てしなく広がっているものかつい忘れがちになる。
ノーラはホッキョクグマと対峙して死を目の当たりにし、「人間も自然の一部である」こと、そして「自分が本当は生きたいと思っている」ことを理解した。このような気付きは、見慣れた日常生活を送っている場合得られにくい。そして、彼女のように自責と後悔の念に苛まれていたのなら尚更だ。
『ナショナルジオグラフィック』2023年5月号にも、“ホッキョクグマに出会うことは夢であり、悪夢でもある。スヴァールバル諸島のホッキョクグマと人間は、時に互いの命を奪うこともある。”と書かれてあった。生と死が隣り合わせの厳しい大自然の中では、「生きていること」そのものが尊く意味のあるものに感じられるのだろう。
ありふれた日常を生きる
小説は、非日常や異世界へ誘ってくれる「どこでもドア」のような存在だ。人間の想像力は、あらゆる冒険を可能にしてくれる。そしてその体験は、時に忘れかけていた感情を呼び起こしてもくれるだろう。
真夜中の図書館で、私はもう一度夢を見た。だが、それは以前見た夢と同じようで、少し違うものだった。「北欧にもまた行きたいし、オーロラも見てみたいし、スヴァールバル諸島にも行ってみたい!」
しかし、それらを叶えられていない今この状況下でも、私はたくさんのものを見て、聞いて、感じることができるのだ。(小説や雑誌は、その一つの手段だ)だから、今自分が見ているこの夢は、分断された未来の「いつか」や「憧れ」のようなものではなく、現在進行形の人生の「選択肢の一つ」に過ぎないのだと思う。
外からは充実し完璧に見える人生だって、中身はほかの人の人生ときっとそこまで変わらない。似たような毎日と挫折とを際限なく繰り返し、傷つき、他人との競争を強いられ続ける。だがそんな中、ふとした折りに美しい何かや息をのむような出来事に出逢うことがある。たぶん本当に意味があるのはそういうものだ。自分が世界の一部であればこそ、そうした場面が巡ってくる。
『ミッドナイト・ライブラリー』の主人公ノーラがこう教えてくれたように、ありふれた日常の中にもっと可能性を感じたい。「美しい何か」や「息をのむような出来事」を見落とさないように、大切にして生きていきたい。今はそう思っている。
【出典】
・マット・ヘイグ著『ミッドナイト・ライブラリー』ハーパーコリンズ・ジャパン
・『ナショナルジオグラフィック』2023年5月号