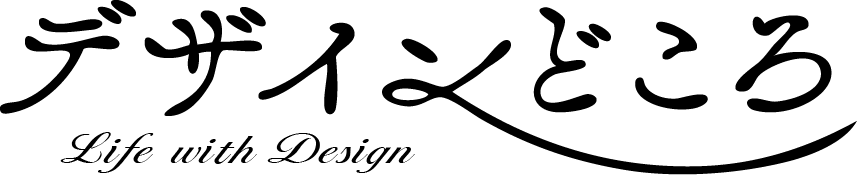2019年の話題になったニュースの一つに、「老後2000万円問題」が挙げられるのではないかと思います。しかし、この国の未来を徒らに悲観していても仕方がありません。そこで、まずは「老後」や「暮らし」に対する多様な価値観を学ぶことにしました。
1. デンマークから学ぶ「暮らし」のデザイン
私は特にデンマークが好きなので、まずはデンマークから学びたいと思います。参考にした本は『北欧流「ふつう」暮らしからよみとく環境デザイン』です。この本は北欧諸国(デンマーク、スウェーデン、フィンランド)で過ごした複数の著者による、「ふつう」に生活している人々の「生活の質」について言及した著書です。
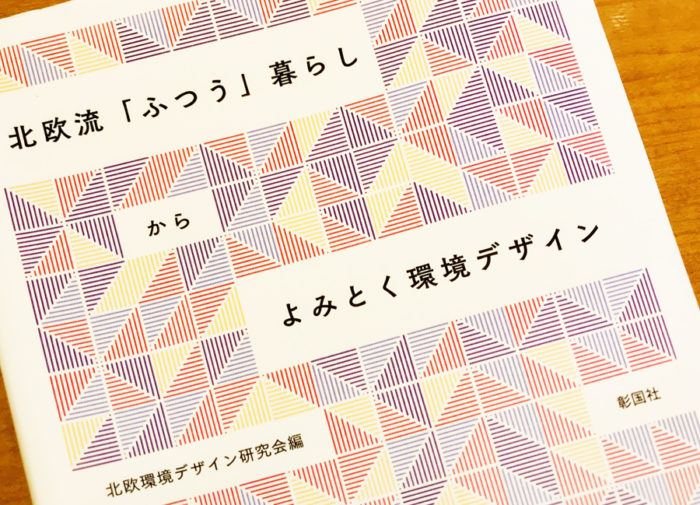 第一に、「生活の質」とは一体何か?本書の序章では、下記のように述べられています。
第一に、「生活の質」とは一体何か?本書の序章では、下記のように述べられています。
北欧において「生活」の質を向上させることは、決して抽象的・観念的な目的なのではない。何か制度や基準をつくって「これは良いことだからこうするべきだ」というように教条主義的に押し付けようとすることでもない。それよりも極力具体的な方法を用いて、なるべく効率的・効果的に達成しようとする、きわめて合理的な考え方に裏打ちされたプロセスが必要であると考えられているように思う。
これを「老後2000万円問題」に置き換えて考えてみます。これは、「2000万円の貯蓄があれば、老後の生活がある程度保証されるだろうから、働き盛りの世代が貯蓄や投資をしやすいような制度を整えるべきだ」といった考えが元になっていると思います。しかし、ここで言うところの「生活の質」は、抽象的・観念的な目的に留まっています。
これを北欧流(より実践的な方法)で考えてみると、「自分が老後どんな生活を送りたいか」ということを考える必要がありますし、そしてその「生活」は単なる憧れや絵空事ではなく、自分自身の「普通の暮らし」として、意義や幸せを感じながら実践できるか、ということだと思うのです。つまり、理想の老後の暮らしを、まだ年をとる前から取り入れてみたり、実際にお年寄りの方と一緒に生活してみたり、そうすることで「これは良いかも」「これは違うなぁ」「今度はこれを試してみよう」ということが理解できます。そして、そのデザイン的プロセスを繰り返していくことで、「生活の質」が合理的かつ自然に向上していくのではないでしょうか。
本書は、アイディアと実践の具体例がたくさん紹介されています。その中で、私が興味を持ったデンマークの「エルダーボーリ」「コレクティブハウス」「エコビレッジ」についてシェアしたいと思います。
2. エルダーボーリ(高齢者住宅)
「エルダーボーリ」とは、高齢者住宅のことです。日本の老人ホームと少し違うのが、「スタッフが常駐しないエルダーボーリが多い」ということと、「要介護になる前から住むことができる」という点が挙げられます。それらを可能としているのが、デンマークの「在宅福祉サービスの充実」です。そして、訪問介護だけで大丈夫なのか、という不安は「環境デザイン(空間の設計)」によって解決することが可能です。具体例として、「トーベックエルダーボーリ」と「セルメアスボーエルダーボーリ」が紹介されています。
まず、「トーベックエルダーボーリ」の特徴です。
- 緑豊かな海辺の小さな街に建つ
- 図書館から100mの立地
- 隣に小さな公園がある
- 敷地内に古い歴史的なホテルの建物が保存活用されて街のコミュニティスペースとして開放
- 各戸に個人庭がある
一番の特徴は、「各戸に個人庭がある」ことだと思います。デンマークの設計者がまずこだわるのは「外部空間の設計」と言われていて、トーベックエルダーボーリの個人庭は、プライベート空間を保ちつつ、自然の住人同士の気配や安否を知ることができる設計になっているそうです。
次に、「セルメアスボーエルダーボーリ」です。
- アクティビティセンターが併設されていて、サークル活動が盛ん
- アクティビティセンターは、60歳以上の同じ市の住民であれば誰でも利用可能
- 地域の住民が、ある時は利用者として、またある時はボランティアとして、積極的に関わる
前述のトーベックエルダーボーリよりも、利用者が能動的に行動することによって、より生活の質が向上する高齢者住宅と言えるでしょう。また、「利用者」「ボランティア」「訪問介護のスタッフ」が、サービスを受ける者と提供する者という一方通行の関係性ではなく、同じ地域に共に暮らす者として、自立しつつも助け合い支え合う姿勢がとても重要になるだろうと思いました。
3. コレクティブハウス(共同・共有する住み方)
「コレクティブハウス」は、生活や空間を複数の世帯で共同・共有する住み方を意味します。日本でも一般的になりつつある「シェアハウス」とは、似ているようで全く違います。コレクティブハウスには「多世代型のコレクティブ」と「高齢者限定のシニアコレクティブ」があります。その歴史は40年余りだそうですが、住む人は少数派だそうです。また、入居希望者は面談をして、住民が住民を選抜するそうです。具体例を二つシェアします。
まず、「ユーストラップサアヴェアケ」の特徴です。
- 共有スペース(食堂・キッチン・リビング・木工室・裁縫室・洗濯室 他)
- 各住戸へ至る中廊下(屋根付きの廊下)空間が広々としていて充実
- 週6回夕食を共にする
次に、「ヤーンストゥベリコミュニティ」です。
- 鋳物工場を増改築した建物
- 合同の食事は週3回、1か月に一度程度食事当番が回ってくる
- 共有スペース(食堂・キッチン・リビング・倉庫・洗濯室 他)
- 外部空間(菜園・果樹園・遊具)
どちらも多世代型コレクティブ。そして、共同の食事の頻度が高いです。コレクティブハウスのような暮らし方が生まれ、続いている背景には、「女性の社会進出」と「核家族化の進行」が挙げられます。食事や子育てなどの労務をシェアして共同化したり、年齢や家族を超えて居住者同士が助け合ったりすることで、互いの生活環境の質が高めることができるそうです。
4. エコビレッジ(持続可能な生活)
最後に「エコビレッジ」を紹介します。“現代社会のライフスタイルを見直し、より持続可能な生活を目指して実践するコミュニティ”のことを意味します。デンマークには50を超えるエコビレッジがあり、人口当たりの数は世界最多だそうです。
デンマークで最初に誕生した「デュッセキレ・エコビレッジ」を例に、主な特徴をシェアします。
- 住宅はセルフビルド
- パッシブソーラーや高断熱による省エネルギー
- 自然素材や廃材を使用
- 職住隣接(近隣で働くか、ホームオフィスの住宅勤務)
- 集会所、クリニック、商店、ベーカリー、カフェ、私立学校がある
- 閉じたコミュニティではない
最後の「閉じたコミュニティではない」というのは、例えば、エコビレッジ内の学校に周辺の地域から通ってくる子供がいたり、またその逆があったり、食糧や電力の全てを自給している訳ではなかったりと、「他を排除する」という考えではなく、より柔軟に「他と交わることで、エコビレッジの考えやアイディアを広めよう」としているように思います。そして、それに共感や賛同した人によって、今後も新たなエコビレッジが誕生していくのではないでしょうか。
デンマークから学ぶ「暮らし」のデザイン。それは、「自立した多様な暮らし」でした。北欧やデンマークは、社会保障が充実した国であると言われます。でも、そこに住まう人々は、“充実した社会保障に守られ、与えられた環境や社会システムを享受する受給者”ではありません。そして、“サポートされるべき立場であろうとも、行政の制度やコミュニティによる支えに、全面的に寄りかかる”ようなことは決してしないのです。つまり、“自分の生活は自分で組み立てて、責任を持って社会と関わる自立した主体”なのです。
だからと言って、日本よりデンマークの方が良い、日本はダメだ、とは思いません。北欧やデンマークから学ぶべきことはたくさんありますが、学ぶだけではなく、自分が暮らす日本で、できることを実践していくことが大事なのだと改めて感じました。